| 尾 | 瀬で熊の目撃数増加 |
|
|
|
| 熊のお話し | |||
| ●尾瀬で熊の目撃数増加 | ●熊は絶滅するのか? | ●ツキノワグマはどんな性格? | ●熊にあったらどうする? |
| ●下のグラフ1は尾瀬保護財団の発表資料をもとに作成した一般のハイカーなどによる目撃件数を年度別に表したグラフです。 これで見ると、目撃件数が急に増えつつあるように思えます。 |
|
| ◆グラフ1 尾瀬におけるツキノワグマ目撃件数 |
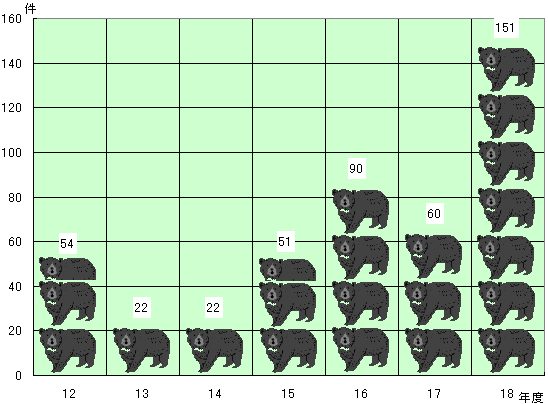 |
| ※尾瀬保護財団発表資料から作成 | |
| ●上のグラフ1では、平成18年度がやけに多くなっていますが、尾瀬保護財団研究員の農学博士橋本幸彦氏のコメントによれば、小熊が人に近づかないようにするために、山の鼻ビジターセンターや財団事務局職員による巡回が2〜数時間おきに実施され、この巡視中の目撃件数を、入山者が目撃したのと同様に目撃記録として記載されたためだと説明しています。そうしたことを割り引いても、目撃件数は増加しているようです。 |
■人のいるところ餌あり
| ●下の図1は尾瀬保護財団が発表したデータを元に、平成12年〜18年のツキノワグマ目撃地点をプロットしたものです。 熊の目撃地点はほぼ尾瀬一帯に分布しています。ツキノワグマは本来臆病だと言われていますが、ハイカーが比較的多く通過する場所で目撃件数が多くなっています。これは言い方を変えれば、ツキノワグマは人のいるところを決して避けていないということです。 前述の監視活動を含め、熊が人に近づかないようにするための早急な対策が必要だと思われます。 |
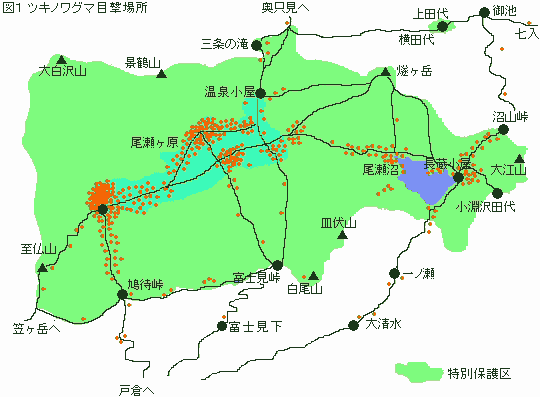 |
|
| ※尾瀬保護財団発表資料から作成 |
■熊は各地で出没数増加
| ●平成18年度は熊に襲われたことが原因による死者5人、重軽傷者130人以上という、被害件数が非常に多いものでした。そのため、捕獲数も史上最多となり、捕獲された熊の多くは危険とみなされて処分されてしまいました。 (朝日新聞:H18.12.13朝刊) ●ではなぜこんなに熊出現が多くなっているのか。ツキノワグマの捕獲数をみると、年によって大量になる「特異年」があります(グラフ2)。どうやら熊の好物であるブナの実の豊作・凶作が影響しているようで、平成15年度はブナの実が大豊作でしたが、平成16年度は凶作だったようです。 |
|
◆グラフ2 全国におけるツキノワグマ有害捕獲数 |
|||
| ※有害鳥獣捕獲 | |||
|
鳥獣法に基づく、鳥獣捕獲許可を受け、銃やワナなどを使用して有害な鳥獣を捕獲する行為。 防護柵等の設置など防除を実施しても被害がくい止められない場合に実施。 生活環境へ悪影響を与える場合、人身への危害又は自然環境を悪化させるさせる場合若しくはそれらの恐れがある場合に適用 |
|||
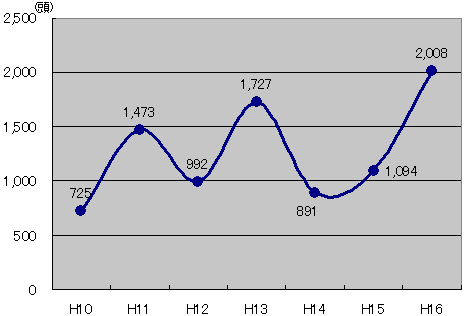 |
|||
|
|
※インターネット自然研究所公表資料を参考に作成 ※捕獲数は都道府県知事と環境大臣による狩猟許可によるツキノワグマ捕獲件数の合計 |
■熊の好物・ブナが不足している
| ●石川県自然保護課のサイト(Q&Aのコーナー)にこれを証明するブナの作況と熊の捕獲数の関係を示したグラフがあります。これによると、ブナの実が豊作の年の翌年は凶作となり、熊の捕獲数が増加しています。また、豊作は2年続くことがなく、周期は不定期となっています。 ●平成18年度もやはり凶作で、前の年の17年度は豊作でした(朝日新聞:H18.12.13朝刊)。このことは、熊の餌となる実を結実するような落葉広葉樹林が減少すれば、必然熊は餌を求めてあちこちへ出現することとなり、ひいては絶滅の危機にも繋がることとなります。 ●熊の出没が増えているその他の原因としては、新聞記事では、開発による森林伐採、過疎化による奥山と人里の境界減少、ハンターの減少などがあると言っています。 環境省の調査では、平成16年秋の北陸地方を中心に発生したツキノワグマの大量出没について、その原因として、 ① 北陸地方の大量出没にはブナの不作の影響があったと考えられたこと ② 里地里山がクマの好適な生息地になりつつある可能性があること ③ 集落周辺に放置されたカキなどの果実や生ゴミなどが誘因になった可能性があること などをあげています。 |
| 熊 | は絶滅する? |
|
|
|
■各地で絶滅危惧種指定されているツキノワグマ
| ●IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは、ツキノワグマの種全体が絶滅危急種に指定されています。 ●日本における熊はヒグマとツキノワグマの2種で、ヒグマは北海道にのみ。ツキノワグマは本州以南に生息すると言われてきましたが、環境省の調査では、九州では絶滅されたと見られており、四国と九州の全域および本州の一部の地域では絶滅もしくは絶滅の危機に直面しています。 そのため、国では、特定地域のツキノワグマを絶滅のおそれがあるとして、地域個体群としてレッドデータブックに掲載しています。また、各都道府県でも独自のデータブックに掲載しています。 |
| ◆環境省レッドデータブック掲載リスト(H14.3現在) |
| ・下北半島のツキノワグマ | |||
| ・紀伊半島のツキノワグマ | |||
| ・九州地方のツキノワグマ | |||
| ・四国山地のツキノワグマ | |||
| ・西中国地域のツキノワグマ | |||
| ・東中国地域のツキノワグマ |
| ◆ツキノワグマに関する都道府県レッドデータブック掲載リスト(H18.12.15現在) |
| 都道府県 | 指定の程度 | |
| 青森県 | 絶滅の恐れがある地域(下北半島) | |
| 岩手県 | 絶滅の恐れはないが減少している。 | |
| 秋田県 | ||
| 群馬県 | 今後も生息情報や環境の変化に十分注目する必要がある種 | |
| 埼玉県 | 絶滅の危機が増大している種 | |
| 東京都 | 地域レベルでは絶滅の危機が増している。 | |
| 神奈川県 | 絶滅の危機に瀕している種 | |
| 山梨県 | 今後も生息情報や環境の変化に十分注目する必要がある種 | |
| 長野県 | 絶滅の恐れがある地域(中信高原・八ヶ岳) | |
| 静岡県 | 絶滅の恐れがある地域(富士地域) | |
| 愛知県 | 絶滅の危機に瀕している種 | |
| 三重県 | 近い将来における絶滅の危険性が高い | |
| 滋賀県 | 県内において存続基盤が脆弱な種 | |
| 京都府 | 絶滅寸前 | |
| 和歌山県 | 絶滅の危機に瀕している種 | |
| 奈良県 | 絶滅の危機に瀕している種 | |
| 兵庫県 | 絶滅の危機に瀕している種 | |
| 鳥取県 | 絶滅の危険が増大している種 | |
| 島根県 | 絶滅の危機に瀕している種 | |
| 岡山県 | 絶滅の危機に瀕している種 | |
| 広島県 | 絶滅の危機に瀕している種 | |
| 山口県 | 絶滅の危険性が極めて高いもの | |
| 徳島県 | 絶滅の危機に瀕している種 | |
| 愛媛県 | 絶滅の危機に瀕している種 | |
| 高知県 | 絶滅の危機に瀕している種 | |
| 熊本県 | 絶滅 | |
| 宮崎県 | 絶滅 |
| ※各都道府県自然保護担当課のレッドデータから抜粋 | |
●餌の豊富な年にたらふく食って、翌年に繁殖が多くなるということは考えられます。尾瀬がどうなのかは不明ですが、地域によっては短期的に増加しているところもあるのかも知れません。しかし確実に言えるのは、熊の棲める地域が少しずつ狭められ、全体としては生息数が減少しているということです。 |
■地球温暖化によりブナの森が消失
| ●森林が減少すると、熊はますます棲息域を狭められ、やがては絶滅へと追い込まれることになります。 ここにちょっと心配なデータがあります。 ●日本の年平均地上気温は、長期的には100年あたり1.06℃の割合で上昇しており、特に1990年代以降、高温となる年が多くなっています。下のグラフ3は東京、前橋、日光の平均気温の推移を表したものです。平均気温は高低を繰り返しながら、徐々に上昇しています。 ●温暖化による気温と降水量の変化は高山植物や森林へもろに悪影響を及ぼし、減少または消失の恐れを生じさせます。森林総合研究所が行った日本におけるブナ林分布の予測計算によれば、2090年に、現在と比較して3.6℃気温が上昇した場合、ブナ林の分布確率50%以上の地域が約9割減少すると予測されています。また、国立環境研究所の予測では、2090年頃までに気温は4.5℃上昇し、九州、四国、中国、紀伊、関東などの各地域でブナ林がほとんど消失する可能性があるとしています。 |
| ◆グラフ3 平均気温の推移 | |
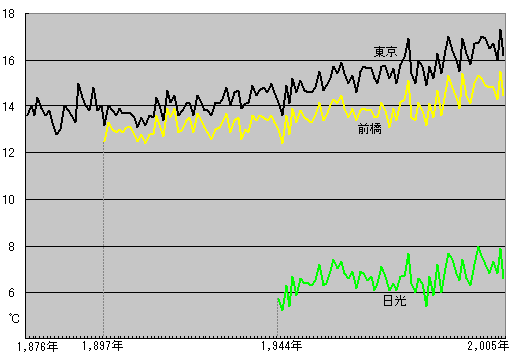 |
| ※気象庁統計資料から作成 |
| ツ | キノワグマはどんな性格? |
|
|
|
■ツキノワグマは恐ろしい生き物か?
| ●ツキノワグマはヒグマほどに力は強くないので、一般的に人間にとっての危険はヒグマと比べて少ないと言われています。(アジア大陸に棲むツキノワグマでは、トラから獲物を奪い取った例もあり、獰猛な面があるようです。) ●日本のツキノワグマは、ツキノワグマの亜種として、ニホンツキノワグマと分類され、本来おとなしい性格で人を襲う習性はないと言われています。 ●積極的に人を襲うことはありませんが、臆病な余りに、出会い頭で驚いて人を襲ったり、小熊を守るために向かってきたりすることがありますので注意が必要です。 ふだんは木の実や昆虫類などを食べる雑食性で、視力が弱く、聴力と嗅覚に頼って行動、生活しています。大型で行動は鈍そうですが、人より速く走ることができます。 ●ツキノワグマは甘い匂いやくさい匂いが大好きです。キャンプ場などでは残飯や食べ物を放置しないようにしてください。 |
■ツキノワグマの特徴(環境省:クマ類出没対応マニュアルなどを参考に作成)
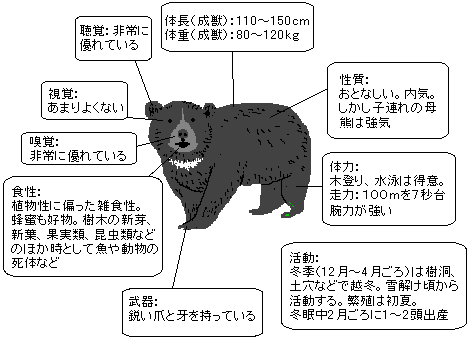
|
| 熊 | にあったらどうする? |
|
|
|
■今の時代、「死んだふり」を信じている人はいないと思いますが・・・・・
| ●小さい頃は「熊にあったら死んだふりしてその場にじっと目を閉じて横たわるのが一番いい」と教わりました。今考えると恐ろしい迷信です。熊にあったら進んで身を提供しろと言っているようなものです。 熊は好奇心が旺盛で、引っ掻いてみたり、咬んでみたりするおそれがあります。熊の強い力で頭や腹をえぐられたら死んだふりどころか、ほんとに死んでしまいます。 ●もうひとつ代表的な迷信に、「熊にあったら高い木に登れ」というものもありました。はっきり言って熊は人間より数倍木登りがうまいです。一般的には熊は体が大きくなると木登りをしないようですが、ツキノワグマは成獣でも木登りをするようです。高い木の枝先近くまで登って木の実を食べている映像や写真を見たことがある人もいると思います。 |
■まず熊に会わないようにする
|
●山はもともと熊の住みかです。そこへ人間の方が分け入って行くわけですから、山での遭遇事故は人間側の責任と言えます。 以下は環境省が発表している対策マニュアルからの抜粋です。 |
||
|
|
①クマに対して自分の存在を知らせることが必要。特に、林内や背の高い藪等の視界の効かないような場所では、鈴など音の出るものを携帯すること。 ②クマの糞や足跡などの痕跡を見つけたら、要注意。 ③二人以上で行動すること。 ④悪天候、夕暮れ時は見にくいので特に注意。 ⑤川や沢の近くでは水音によって、接近するまで気がつかないこともある。 ⑥食品やごみは必ず持ち帰ること。食品またはそのにおいなどにクマが馴れて人里に引き寄せる要因になる。 |
|
■熊に会ってしまったら・・・・・
| ●以下も環境省が発表している対策マニュアルからの抜粋です。 |
|
①クマがこちらに気づいていない時は、ゆっくりとクマから見えない方向まで離れる。 ②クマがこちらに気づいている場合は、周囲の状況に気を配りながら逆の方向にゆっくり離れる。 ③クマが気づいて近づいてくる場合は、クマの動きを十分確認しながら、ゆっくりと後退。 ④子グマに出会っても近寄ってはダメ!子グマの近くには母グマがいる可能性が高いため、速やかにその場所を離れること。 |
|
●熊の方が近づいてきたときに、冷静にゆっくり行動できるかどうか疑問ですが、とにかく走ったりしてはいけないようです。 参考までに「熊に会ったらどうする」という本から抜粋。(福井県のHPで紹介しているものです。) |
| 方 法 | 可否 | 可否の説明 | |
| 立ったまま大声で助けを求める | × | ・身近に助ける人がいなければ意味がない。 | |
| 地面に寝て死んだ振りをする | × | ・べたりと寝そべると体が小さく見え、かえって熊が好奇心を起す ・熊は新鮮な死体を食べるかも知れない。 |
|
| 走って逃げる | × | ・相手を刺激するだけ。 | |
| 木に登る | × | ・熊には通用しない | |
| 四つん這いになって吠える | × | ・目の高さを低くするのでまずい。 ・吠えると熊は敵対行動をとる。 |
|
| 静かに後ずさりする | △ | ・準正解、これで難を逃れた人は多い。 | |
| 荷物を置いて時間を稼いで逃げる | △ | ・準正解、これで難を逃れた人は多い | |
| 立ち止まったまま話しかける | ○ | ・動かないので熊の行動を刺激しない(熊側は態度を決めかねる) ・話しかけられることへの戸惑いがある。アメリカの西部開拓史にはこのような話が沢山出てきます。アイヌの人たちもこの手を使ったそうです。 |
|