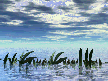|
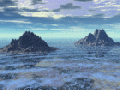 |
至仏山から景鶴山にかけて、秩父古生層と呼ばれる約5億年前の古い地層が見られます。尾瀬でもっとも古い地層で、至仏山や景鶴山は隆起によってできた山と言われます。 |
 |
 |
火山活動が繰り返され、溶岩流で川がせき止められ大きな湖ができます。燧ヶ岳などの噴火による溶岩流が只見川をせき止めて、現在の尾瀬沼や尾瀬ヶ原の元になる湖をつくったと言われます。 |
 |
 |
せき止められ湖に周りから土砂が流入したり、植物が進入したりします。 徐々に浅くなった湖に、ヨシ、スゲ、ミズゴケなどが腐敗しないまま堆積して泥炭化していき、湿原が形成されていきます。 |
| ※なお、1972年にボーリング調査が行われた結果、地下81mまでの場所では、ここに湖があったという証拠が得られませんでした。このため、尾瀬ヶ原の成立については不明です。尾瀬沼については、約1万年前に、火山の燧ケ岳が誕生し、火山活動による溶岩などによって、盆地の東半分がせき止められ、これにより尾瀬沼が成立したと考えられています。 | ||