 尾瀬という地名が初めて記録に見られるようになったのは、会津松平家初代藩主、保科正之が編纂した「会津風土記」(寛文6年
1,666年)といわれています。同記録には小瀬沼という記述があり、奥州(福島)と上野(群馬)の境界とされています。表記は「尾瀬」ではなく、「小瀬」となっています。
尾瀬という地名が初めて記録に見られるようになったのは、会津松平家初代藩主、保科正之が編纂した「会津風土記」(寛文6年
1,666年)といわれています。同記録には小瀬沼という記述があり、奥州(福島)と上野(群馬)の境界とされています。表記は「尾瀬」ではなく、「小瀬」となっています。これ以前は「さかひ沼」と呼ばれ、やはり国境となっていたためそう呼ばれていたと思われます。
一方、安永3年(1,774年)の「上野国史」には、「沼峠 駒ヶ岳ノ東に在り 上野越後陸奥の界ナリ 山上にアリ尾瀬沼ト云フ・・・・・」という記述がみられます。また、慶應4年(1,868年)の「奥羽国群分色図」(作者:景山致恭)には、「駒ヶ岳」の東に「尾セヶ原」という表記があります。
この駒ヶ岳は現在の越後駒ヶ岳と思われますが、尾瀬ヶ原や尾瀬沼は正確には越後駒ヶ岳から南東に位置しています。
このことから会津(福島)では昔から「小瀬」といい、上野(群馬)では「尾瀬」と呼んでいたと思われます。
※保科正之は、徳川秀忠の子だが、母が側室ゆえ武田信玄の娘見性院に養育され、信州高遠の城主保科正光の養子となった。三代将軍家光は正之を実弟として、最上山形、続いて会津の城主とした。保科正之は名宰相と謳われた人。
※景山致恭(かげやま むねやす)は江戸時代の学者。「奥羽国群分色図」は大政奉還の翌年に編纂された。(地図は復刻版として人文社が発行しており、書店でも購入できます。)。では、"尾瀬"という呼称は、何に由来するのでしょうか。
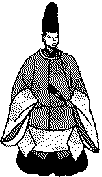 奥只見の銀山平には、尾瀬三郎房利の像が立っています。像の説明書きに下記のような物語が記されています。
奥只見の銀山平には、尾瀬三郎房利の像が立っています。像の説明書きに下記のような物語が記されています。 片品村史によれば、治承2年(1,178年)ごろ(高倉宮の逃避行で尾瀬を通行した時期)、尾瀬中納言という人があったといいます。それから時が経ち、正中2年(1,325年 正中の変の後)、時の尾瀬城主尾瀬兵衛は、後醗醐天皇に味方したため、北条範貞に亡ぼされました。このとき尾瀬氏はついに滅亡したといいます。
片品村史によれば、治承2年(1,178年)ごろ(高倉宮の逃避行で尾瀬を通行した時期)、尾瀬中納言という人があったといいます。それから時が経ち、正中2年(1,325年 正中の変の後)、時の尾瀬城主尾瀬兵衛は、後醗醐天皇に味方したため、北条範貞に亡ぼされました。このとき尾瀬氏はついに滅亡したといいます。 日本四大姓とは、源、平、藤原、橘の4つと言われ、奈良時代から平安時代にかけて公卿になることの出来る名門の姓とされていました。
日本四大姓とは、源、平、藤原、橘の4つと言われ、奈良時代から平安時代にかけて公卿になることの出来る名門の姓とされていました。 檜枝岐歌舞伎で有名な袖萩とお君の母子の像が、歌舞伎舞台へと続く小道の中ほどに立っています。檜枝岐歌舞伎の人気演目「奥州安達ヶ原袖萩祭文の段」。安倍貞任の妻でありながら盲目となって流浪する、萩袖とその娘のお君の悲哀のストーリー。
檜枝岐歌舞伎で有名な袖萩とお君の母子の像が、歌舞伎舞台へと続く小道の中ほどに立っています。檜枝岐歌舞伎の人気演目「奥州安達ヶ原袖萩祭文の段」。安倍貞任の妻でありながら盲目となって流浪する、萩袖とその娘のお君の悲哀のストーリー。