| 2,003年11月1日~11月3日 |
|
10月23日に尾瀬に初雪が降った。ついに、冬の使者の到来だ。昨年もこの時季から、一気に冬に突入していったのだ。今年も雪や霜に会えるかもしれないと期待して、山小屋を予約した。 ところが、出かける当日の天気図は、南から暖かい風が入りやすい気圧配置になっていた。今年は、白い世界は無理かとやや期待はずれの感じを抱きながら出かけることになった。 |
|
OZE-Report
2003 VOL.7 report by HIDEO MAKISHIMA |
●写真をクリックすると拡大します。(JavaScript
On)
※なお、一部拡大しない画像もありますが御了承ください。
| 2003年11月1日(土) 天気 晴 万歩計の歩数 24,410歩 | |
|
7:39 浦和 →(水上1号)→9:25 沼田 9:35 →(バス)→ 11:05 戸倉 11:10 →(バス)→ 11:30 鳩待峠(昼食) 12:00 → 12:35 山ノ鼻・研究見本園 13:15 →14:45 牛首分岐 → 16:00 竜宮十字 → 16:35 竜宮小屋 泊 |
|
| 2003年11月2日(日) 天気 霧後晴 万歩計の歩数 41,911歩 | |
|
3:40 竜宮小屋 → 5:00 中田代の地塘 → 7:05 下ノ大堀川 → 8:00 竜宮小屋 8:30 → 9:40 ヨッピ分岐 9:45 → 10:40 牛首分岐 → 10:50 上ノ大堀川 → 11:05 牛首分岐 → 11:45 竜宮小屋 → 12:15 見晴(昼食) 12:35 → 13:45 白砂峠 → 14:10 沼尻 14:25 → 15:35 長蔵小屋 泊 |
|
| 2003年11月3日(月) 天気 早朝晴後雨 万歩計の歩数 30,005歩 | |
|
4:25 元長蔵小屋付近 6:40 → 6:50 大江川湿原 7:30 → 7:35 長蔵小屋 9:00 → 9:15 三平下 9:25 → 9:40 三平峠 → 10:05 岩清水 → 10:35 一ノ瀬 → 11:25 大清水 12:05 →(バス)→ 13:45 沼田 13:55 → 16:20 浦和 |
|
|
後 記 |
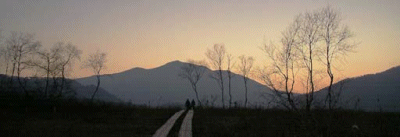 |
|
携行カメラ CONTAX167MT |
| 参考 檜枝岐の気象参考 | ||||
| 月 日 | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 日照時間(時間) |
| 11月1日 | 19.5 | 4.8 | 0 | 4.1 |
| 11月2日 | 20.5 | 4.6 | 0 | 5.4 |
| 11月3日 | 17.7 | 5.6 | 6 | 0.0 |